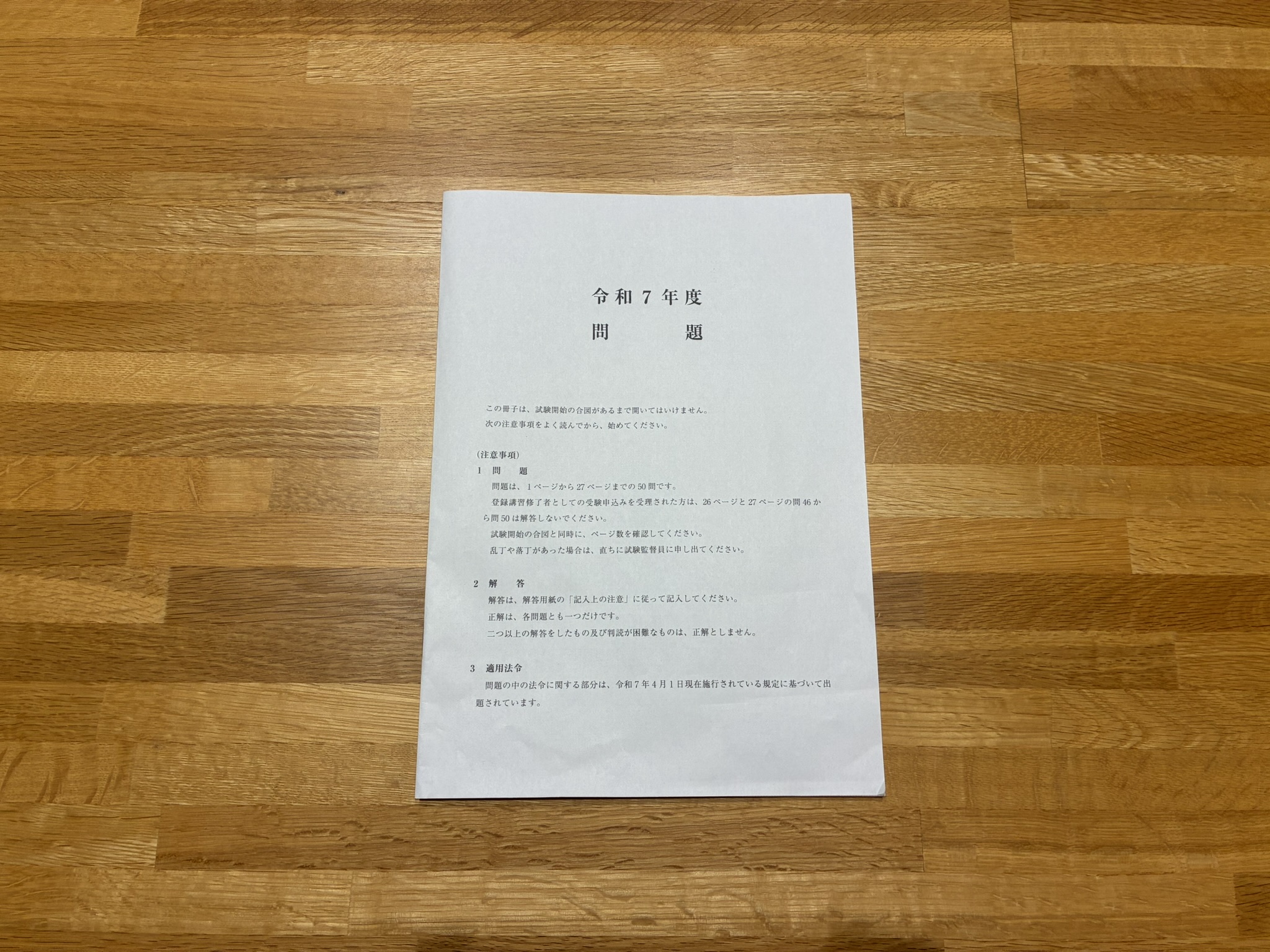資格試験 4択問題の勉強方法
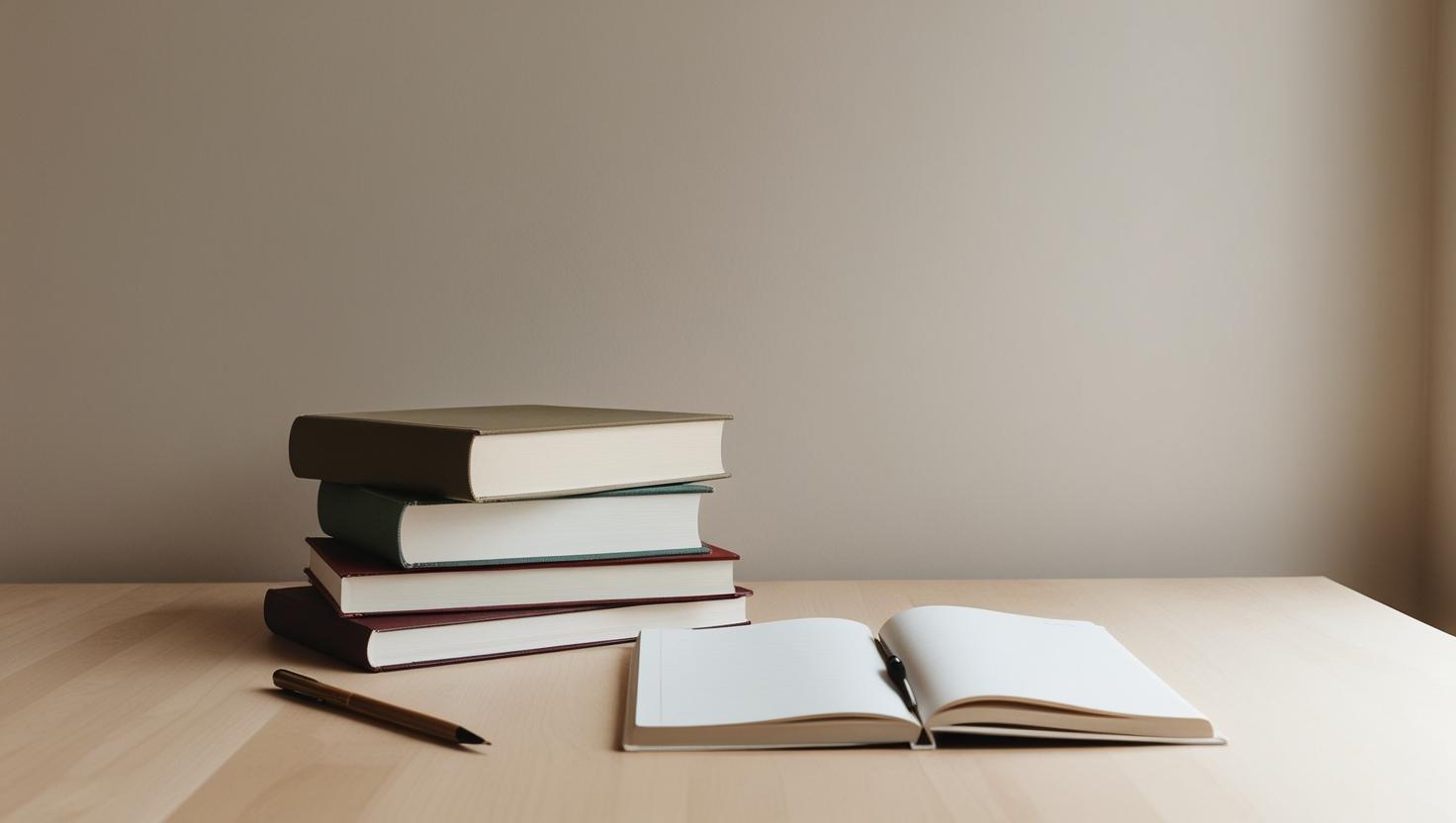
資格試験ではよくあるマークシートの4択問題。こちらの効率の良い勉強方法、コツを紹介します。


過去問は直列ではなく並列に解く
資格試験の4択問題は過去問からの類似問題の出題率が高く、以前の記事でも書きましたが過去問をベースに勉強し、参考書を辞書変わりにする方が効率が良いです。
その際、過去問を令和6年の問1、2、3…、令和5年の問1、2、3…、令和4年の問1、2、3…というように、年度ごとに解いていく人も多いと思います。
年度によって出題の有無、出題数にばらつきはありますが、資格試験は問1は○○分野、問2は□□分野、問3は△△分野…と分野ごとに問題番号、問題数がある程度決まっていることが多いです。
そこで、令和6年の○○分野、令和5年の○○分野、令和4年の○○分野…と同じ分野を続けて解くことで、出題傾向、重要な文章、覚えるべき内容が分かりやすくなり、圧倒的に理解が早まります。
当ブログでは過去問を年度ごとに解くことを直列の勉強法、分野ごとに解くことを並列の勉強法と定義します。
参考書によっては分野ごとの出題率を記載しているものがありますが、気にせず全ての分野を勉強しましょう。資格によっては手を抜ける分野もありますが、人によって持っている知識、得意不得意は違うため、その判断は過去問をそれなりに解いてからで十分です。
並列の勉強法の参考例
例として挙げれば、コンクリート主任技士試験の4択では問3もしくは問4で化学混和剤に関する問題が1問出題されることが多いです。
参考書の化学混和剤部分のテキストにはJIS A 6204の性能表を記載しているのがほとんどで、規定された数値が多すぎて覚えるのが大変で、そもそも全て覚える必要があるのか、どの数字が重要なのか、点数を取るために必要な知識が分かりません。
そこでテキストを見るのをやめ、並列の勉強法を用いて化学混和剤分野の問題だけを解き続けることで性能表の中での必要な知識を先に知ることができます。
以下、自分が混和剤の分野を並列で勉強し、性能表の中で必要だと考えた知識を記載します。
- ブリーディング量の比の上限値が規定されているのは減水剤(遅延形のみ)、AE減水剤、高性能AE減水剤のみ。減水剤は遅延形のみで標準形、促進形には規定無し。規定の数値まで覚える必要無し。AE剤が引っ掛けで出題されることが多い。
- 減水率の規定は減水剤4%以上(標準形)、AE剤6%以上、AE減水剤10%以上(標準形)、高性能減水剤12%以上、高性能AE減水剤18%以上(標準形)、流動化剤は規定無し。遅延形、促進形の数値は覚える必要無し。流動化剤が引っ掛けで出題されることが多い。
- 性能表の相対動弾性係数=凍結融解に対する抵抗性となり、凍結融解に対する抵抗性が規定されているのはAE剤、AE減水剤、高性能AE減水剤、流動化剤。AEが付くもの+流動化剤と覚える。数値まで覚える必要無し。
- スランプと空気量の経時変化量が規定されているのは高性能AE減水剤と流動化剤のみ。規定の数値まで覚える必要無し。AE減水剤が引っ掛けで出題されることが多い。
混和剤の分野で必要な知識は性能表以外にもありますが、少なくとも性能表の中では上記知識が頭に入っていれば十分です。
性能表にあれだけ数値の記載があっても、数値が出題されるのはほぼ減水率の規定のみで他は規定されているかどうかのみ。リンクの性能表には記載がありますが、参考書記載の性能表には相対動弾性係数=凍結融解に対する抵抗性の記載もほとんどありません。
確認のため参考書の性能表を見る場合でも、知識無しで30分見るより上記知識を持って2分だけ見る方が効率が良いと思います。
これらの作業を全ての分野、項目で繰り返し行うことで非常に効率の良い勉強をすることができ、直列の勉強法のみの他受験者と差がつきます。
施工管理技士試験などと違い、コンクリート技士、主任技士、診断士試験は毎年上位○○%を合格にする相対評価の試験です。他の受験者とどうやって差をつけるか、違いを出すか、といった思考も大切になります。
ただし、並列の勉強方は同じ分野の問題が続くため、完全に理解していなくても慣れで答えられてしまうこともあり、ある程度勉強が進んだ際には直列での勉強も行い、知識の定着度を確認することも必要です。
自分はコンクリート診断士受験の際、どうしても時間が足りなくて直列の勉強をほとんどやらず、本番で並列の勉強で覚えたと思っていた問題を間違えてしまい、やはり直列の勉強も必要だと改めて実感しました。
コンクリート主任技士、診断士レベルの4択の場合、過去問でよく出る択が2つ、文面を変えているが過去問で学んだ知識があれば何とか分かる択が1つ、過去問、テキストに記載の無い難解な択が1つの計4択になる場合も多く、不合格者でもそれらを2択まで絞れる人は割といると思います。
文面を変えているが過去問で学んだ知識があれば何とか分かる択、をいかに理解できるかも合格、不合格の分かれ目になってきます。
過去問は何年分解くか
市販の参考書では通しで直近2年分が巻末に記載、出題率の高い問題の抜粋でも直近5年程度のものが多いでしょうか。
正直言って全然足りません。上記期間のみでは出題傾向を掴みきれず、6~10年前の問題が出題されることもあります。
最低でも10年分、出来れば20年分ぐらいが理想です。実際不合格者で20年分の過去問を解いている人はほぼいないと思いますし、案外こういうところで差が付きます。
20年も前だと出題傾向が変わっていて効率が落ちることもあるため、資格によっては直近10年分を重点的にやり、11~20年分は少し力を抜くなどの割り振りも有効です。
教材の選び方
そもそもの前提として、参考書、その他教材の質はその資格の受験者数に比例して上がります。需要の多い場所により多くのお金、人員を掛けるのは当然ですからね。
建設業界は不人気業種のため教材全般の質が低く、民間資格であるコンクリート技士、主任技士、診断士の教材の質は施工管理などの教材よりさらに数段質が下がります。
解説部分の○○の上限値が規定されている、の上限値が下限値に誤植されているなどはかわいいもので、そもそもの回答と解説自体が間違っていたりもします。さらには直近2年分の過去問を記載と謳っていても、解答が〇×のみで解説を放棄しているものすらあります笑。
並列の勉強をメインにする上では、分野毎に過去問が割り振られている教材が必須となります。本当は分野ごとに過去20年分の過去問全てが割り振られ、丁寧な解説付きのアプリ、参考書があれば理想ですが、中々ありません。
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士はappleストアで検索上位に出てレビュー数の多い1級○○施工管理技士 受験対策というアプリがあるためiPhoneユーザーはそれ1択です。自分も使っていました。
2級用はアプリの質が下がるため、いずれ1級も取得したい場合はじめからこの1級用アプリでも良いとは思います。分野ごとに過去問を解け、後で復習したい問題にチェックを付けれたり、解説の他、解答中にも関連資料を見れたりと結構便利です。
施工管理技士の一次検定の勉強はアプリメインで良いため、参考書は2次検定の記述部分で選ぶと良いです。できる限り多くの期間の問題が記載されているのが前提ですが、人によって参考になる工種、表現も異なるため、複数買って参考になりそうな部分を抜き出していくのがおすすめです。
記述があり1冊で完結する参考書が少ない建設系資格では、少し古い参考書というのも中古市場で一定の需要があるため、合格後はそこそこの価格で売却できることも多いです。
自分も中古の参考書は買っていましたが、あくまで記述文章の参考のためであり、JIS規格や法令関係などは改正があるため最新のもので学んでください。特に建設業法は近年試験に出る内容の改正もありました。
運行管理者は当時はありませんでしたが、現在は検索すると1つ評価の高いアプリが出てくるため、自分が今から取得するならまずはそれを使ってみると思います。
法令関係の資格となるため参考書は最新のものを勧めますが、正直アプリのみで合格できるような気もするので、まずはアプリから勉強を始めてみて、必要に感じたら参考書を購入でも良いと思います。
コンクリート技士、主任技士、診断士については、アプリ、PCソフト、他有料サイトでおすすめできるものは正直ありません。実際色々使ってみましたが、出題率の高い問題だけ抜粋しすぎている、解説が不十分、収録年度が少なすぎる、間違いが多いなど…前提にも書きましたが中々に酷いです。
消去法で参考書がメインになりますが、4択問題が分野毎に割り振られているものを複数購入する方が良いです。1冊では問題が抜粋されすぎて不十分で、完璧に覚えてギリギリ合格点に届くかなぐらいの感覚です。
過去問についても通しで記載があるのは過去2年程度が多く、コンクリート主任技士、診断士試験において複数参考書を購入する場合、中古で過去の様々な年度のものを購入するのがおすすめです。コンクリート技士はそこまでやらなくても合格できるとは思いますが。
教材の質が低い資格の場合、複数の参考書で過去問を解き続け、その中で重要だと感じた文章、自分が例に挙げた必要な知識などをWordなどの文章ソフトにまとめることを推奨します。最初は手間が掛かりますが繰り返し必要な知識を確認でき、AI音声に読み込ませることですきま時間の聴く勉強にも使えます。
この作業になるとスマホよりパソコンの方が圧倒的に効率が良く、パソコン推奨です。ちなみに自分は音読さんというサイトでmp3で作成してiPhoneに入れていました。
AI音声についてはYouTubeに過去問の選択肢、解答、解説を読み上げる動画などありますが、個人的にそれらはおすすめしません。
ながら作業で聴く場合、選択肢を全て読み上げられても覚えきれず、視覚を使っての比較もできません。聴いている時点で正誤が分からない場合はインプットして良い情報かも分からず、視覚無しでインプット速度も落ちた上で完全に理解している内容を繰り返し聴くこともあり非常に効率が悪いです。
聴く勉強は自分にとって必要な情報のインプットのみに徹するべき、というのが自分の考えです。現状は自作した方が効率良くインプットできます。
4択問題の文章を活用する
例えば4択問題で不適当なものを1つ選ぶ場合、当然残り3つは正しい選択肢となります。その正しい選択肢は他年度で出題されたり、文章の一部を変えて不適当な選択肢として出題されることもあります。
不正解の1つにしか解説のない教材もありますが、1問で4つ学ぶという意識が大事です。
また、記述のある試験では、4択問題の規定、工法、調査法などの文章が記述の解答として活用できるものも少なくありません。
記述の解答は運営組織から公表されず、実際の解答基準は誰にも分かりません。その中で4択問題の文章というのは、運営組織が公に出している数少ない文章となります。解答基準が分からない以上、記述問題にて運営組織が公に出している文章で解答するというのは合理的です。
ちなみにコンクリート標準示方書、労働安全衛生法、JIS規格など出典元の資料がある場合も、そちらの記載と同じ文章を使う方が良いと思います。
そのため、記述のある試験では、4択問題で最低限の基礎を学んだ段階で記述問題にも目を通すのが有効です。それにより4択問題の勉強をしつつ、記述問題で使う材料を拾い集めていくこともでき勉強の効率が上がります。
まとめ
参考書は色々手を出さずに1冊決めてやれという人もいますが、記載したように記述文章の内容が異なる、抜粋され過ぎている、過去問の収録が少ないことに加え、人によって合う合わないも違います。重複する内容についても、それだけ出題率の高い重要な内容とも言えます。
自分はそういった固定観念も無いため複数購入しますし、特に記述文章作成時は参考書を2~3冊広げ、パソコンで関連する団体の資料なども見ながら作成しています。
我流で勉強してきた自分がたどり着いた考えになりますが、この記事の勉強法で4択問題は十分対応できると思っています。記述についてはまずは7月に試験のあるコンクリート診断士から、資格ごとに掘り下げていく予定です。