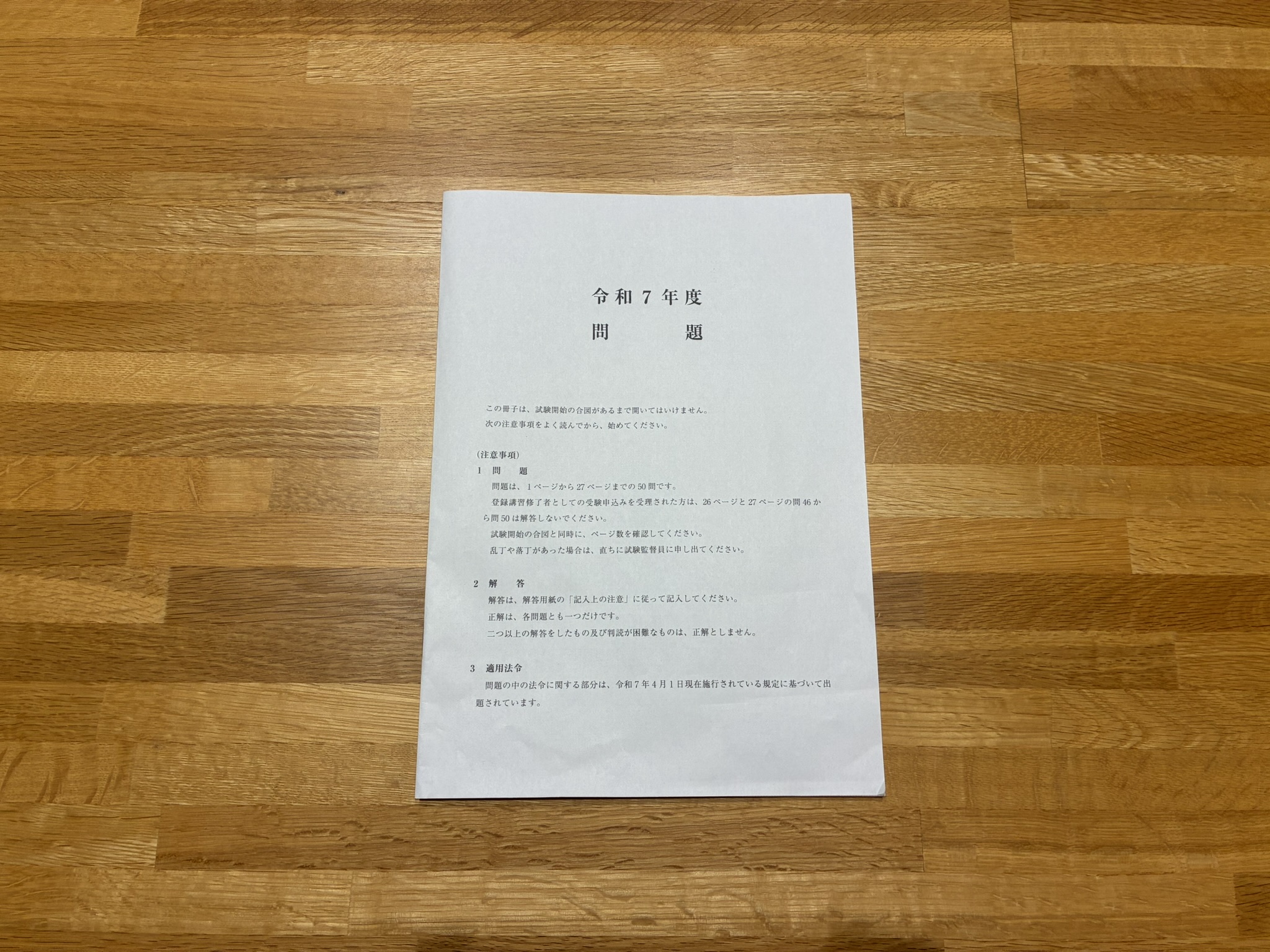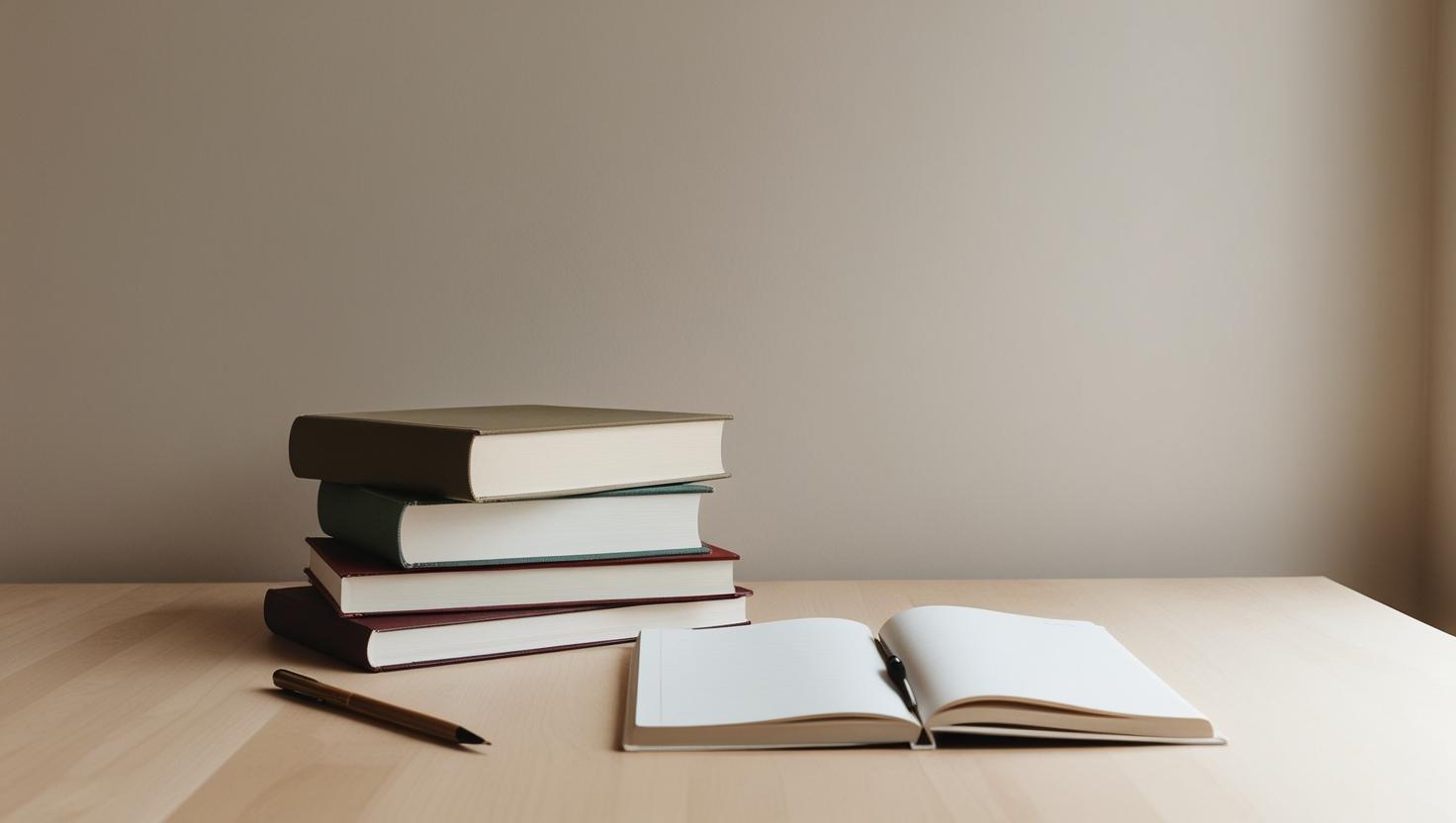資格試験 基本の考え

仕事柄建設業の資格を取ることが多かったため、その中で身に着けた自分なりのノウハウを記事にしてみます。同じ資格、同レベルの資格取得を目指している方の参考になれば幸いです。
4択、記述の勉強方法の前に、まずは基本となる考え方を書いていきます。
これまで取得した資格
- 2級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 運行管理者(貨物)
- 運行管理者(旅客)
- コンクリート技士
- コンクリート主任技士
- コンクリート診断士
- 宅地建物取引士(2025年11月追加)
資格取得していく中で勉強方法の試行錯誤を重ね、最適化し続けることで自分は上記資格を全て一発合格することが出来ました。
大して学の無い自分の経験に基づいたノウハウのため、人によっては大学の教授が監修した参考書より再現性の高い部分があるかもしれません。
自分の考える受験勉強と資格勉強の違い
目標にする点数の違い
大学受験を例に挙げると、ボクシングの階級分けすら霞んで見えるほど偏差値ごとに細かく大学が用意されており、受験戦争に参加していない自分ですら私立大学多すぎないかと思うほどです。
点数に例えると、100点なら○○大学、90点なら□□大学、50点なら△△大学といった具合に点数を取った分だけレベルの高い大学へ入学でき、努力が報われやすい非常に公平な制度だと思います。
そのため、100点を目指して1点でも多くとれるよう努力することには大きな意味があります。
一方資格試験は60~70点前後で合格になるものが多く、結果は合格、不合格の2種類のみ。高得点を取っても合格後の講習や受験料が免除になることもありません。
逆にあと1点足りずに不合格になったとしても、点数が公表されないことを逆手にとって会社、上司へ合格ラインギリギリの点数で報告する不合格者もいるため、信じてもらえないことも多いでしょう笑。
合格するまでは終わらず、挽回のチャンスも大抵は1年後となり、その間は不合格者として過ごすことにもなります。
このように、合格点に届かないと努力は報われないが、必要以上に点を取りすぎてしまっても報われないのが資格試験です。
また、一般的に40点→70点にする勉強と、90点→100点にする勉強では後者の方が膨大な労力が掛かります。そのため、確実に合格しつつ余分に勉強をしすぎない90点程度を目指すのが最も効率が良いというのが自分の考えです。
もちろん資格は取得して終わりではなく、その資格を取ってからどう生かすかも大事で、その中では上記の余分な勉強というのが役立つこともあります。
が、まずは資格と取得しないことには始まらず、余分な勉強は取得した後にすれば良いだけです。
勉強方法の違い
大学受験は教科数も多く、出題範囲も広いです。その分中学~高校にかけてたくさんの授業、テストを受け、予習、復習を繰り返し段階を踏んで基礎~応用まで学んでいきます。
資格試験は出題範囲は限られますが専門的な内容が多く、難易度が高くなるほど一般の参考書、ネット上では答えを探せないような深い問題も出題されます。その代わり、過去問から似た問題の出題率も高いです。
そのため、学校の授業のように教科書を読んでから問題を解くより、いきなり過去問から解き始める方が効率が良いです。当然はじめは分からないと思うので、すぐ解答と解説を見ます。
その際理解できなくても構いません。どうせ理解できるまで何度も解くことになるので。
過去問をベースに勉強をして、参考書は辞書変わりにするイメージです。どのような問題が出るか分かってから参考書を読むことで、どの部分が重要か分かり理解が深まります。
参考書は規定された内容を1から10まで記載していることも多く、試験問題に直結しない内容もあるため丸暗記しようとするのは非常に効率が悪いです。
受験者の立場の違い
大学受験する高校生の場合、大抵の人は親の管理下に置かれ自由になるお金、行ける場所も限られており、部活、家庭の事情などあれど基本的に勉強以外の選択肢が少なく、おのずと勉強せざるを得ない環境になります。
資格試験は社会人で取得しようとする人が圧倒的に多く、社会人には給与所得があり大半は学生より多くのお金があります。世の中は欲望を満たすためのコンテンツで溢れかえっており、多少のお金があればそれらのコンテンツの多くを楽しむことができます。
経済的に自立もしていれば、親から勉強しろと騒がれることはありません。資格を取得出来なくて出世に響く、携われる業務に制限が出る、資格手当が貰えないなどあっても、会社をクビになることはほとんどありません。現状維持は可能ということです。
1日は誰でも等しく24時間で、仕事、家庭、日常生活の時間を除いたものが自由時間となります。上記の欲望を満たすコンテンツに資格の勉強を加えた上で優先順位を付け、自由時間の中に資格の勉強を割り振っていかなければなりません。
これは家計管理、株式投資にも通じる大切な考え方です。自分の周りで資格試験に落ち続ける人は、ほぼ全員この割り振りが出来ていませんでした。
すなわち、資格試験においては自身の欲望をコントロールすることが重要と言えます。
建設業資格試験の近年のトレンド
資格試験にはトレンドというものがあり、それらは時代の流れや世間で問題になった事件、ニュースなどの影響で出題傾向も変わり、特に記述問題では顕著です。
具体的な名称は出しませんが、多数の死者を出した事故、偽装問題、老朽化問題、環境汚染問題などです。
自分が取得してきた建設業資格全般では、SDGsの影響もあり環境負荷軽減、人手不足の影響での生産性向上が近年のトレンドで、20年近くの過去問を比べてもそれらに関する問いが明らかに増えています。
また、記述の解答では○○に関する記述は除く、表記以外で□点△△を挙げよ、具体的な●●名とその理由を述べよ、などといった、より専門的、実践的、具体的な内容を求められることも増えています。
それらについては資格ごとに個別の記事で書いていく予定ですが、今後もこのトレンドは継続すると思われますし、あらかじめ下準備をすれば現状対応可能です。
有料講座は必要か
資格試験においては、予備校のような有料講座も多数あります。
自分としてはそれらは必要無いと思っています。なぜなら人によって業務で学ぶ知識、必要な勉強に偏りがあるからです。
建設業資格の有料講座の場合、大抵は特定の分野、受講者のレベル毎に講座が分かれておらず、出題範囲すべてを網羅した講座をみな一律で受講します。
例えば一級施工管理技士の資格を有して現場経験もある人がコンクリート技士試験の講座を受けた場合、コンクリートの施工に関する分野は既に知識を持っており、講座のその部分から得られる知識は大して無いと思います。
逆にセメントの細かい成分については過去の試験や業務で知識を得る機会が少なく、その部分を重点的に勉強した方が効率が良いです。
現場、工場、発注者、設計者…携わる業務によって知識も大きく異なり、それぞれ合格に必要な勉強内容は異なります。
あくまで資格試験のみに限ればですが、合格点数を取ることのみが目的であり、点数アップに繋がらない勉強は無意味どころか、その間点数アップに繋がる勉強の時間を失うという機会損失になります。
数千円の有料アプリ、有料動画程度なら利用してみるのも良いですが、講座は数万~数十万掛かるものも多く、それに見合う費用対効果は得られないと思っています。
人によって1人で勉強ができない、知識がなく1から誰かに教えてもらいたい、大金を掛けるから本気になれるなど様々で、講座を全て否定するわけではありませんが、自分は講座に支払うお金を稼ぐ時間で1問でも多く過去問を解きましょう、というスタンスです。
ただし、建設業の資格というのは世間一般から見れば不人気業種のニッチ資格です。人気資格と違い世に出回っている勉強のための参考書、ホームページ、アプリ、動画など総じて質が低く、1つで完結するものは自分の知る限り1つもありません。
勉強の効率を上げるには受験者側で工夫していく必要があります。
まとめ
自分の考える資格試験勉強の基本となる考え方について書いてみました。
基本ということでフワッとした内容も多く、今後の記事で深く掘り下げていく予定です。
本当の意味で頭の良し悪しが影響するのは司法試験、公認会計士などの最難関試験で、自分が取得した資格で言えば、頭の良し悪しや効率は勉強時間で十分カバーできる程度の資格です。
極論を言えば合格するまで勉強すれば100%合格するわけで、不合格者の大半は勉強時間が足りていないだけだと思います。勉強しない理由探しをしている間に1問でも過去問を解きましょう!