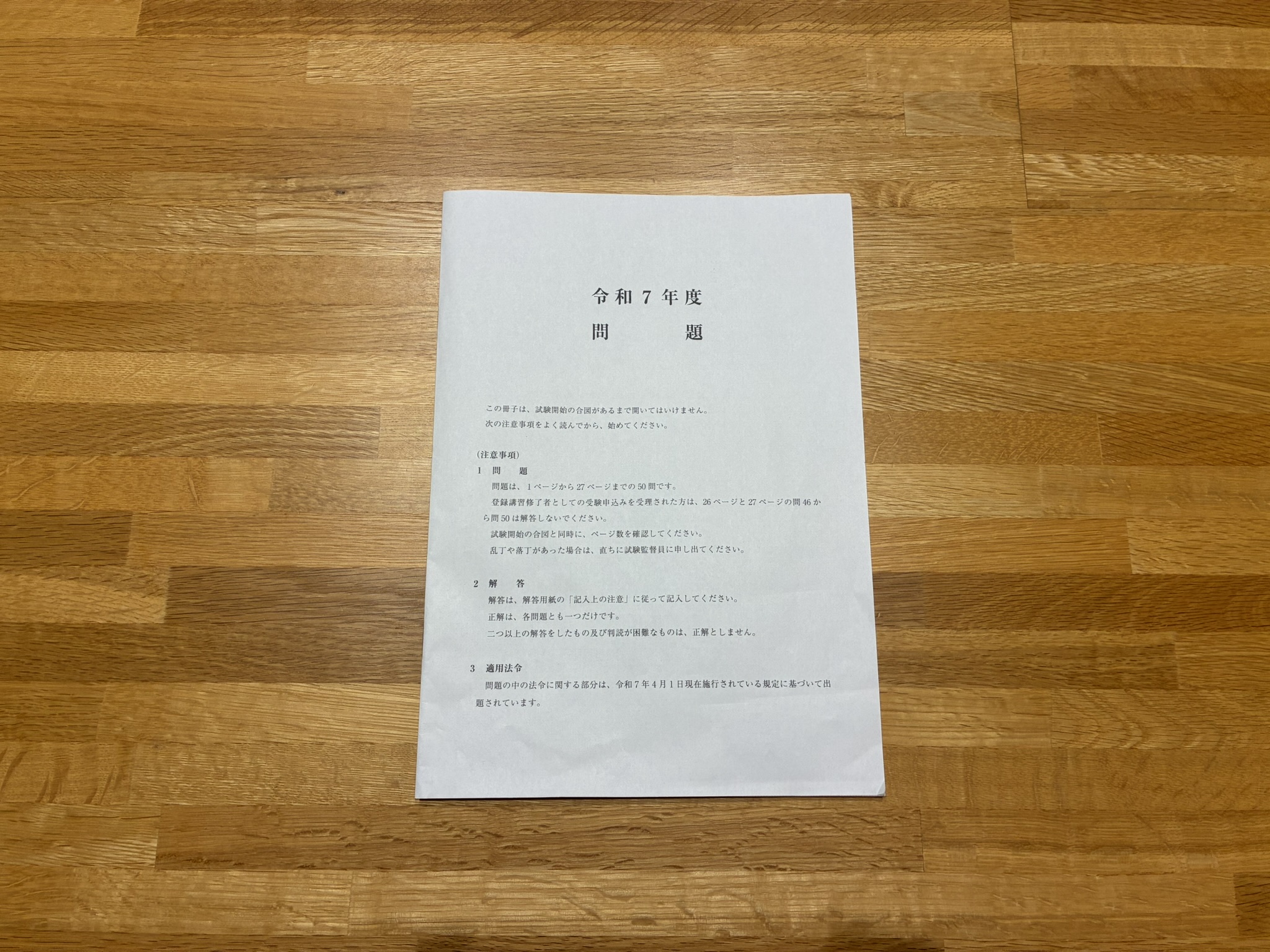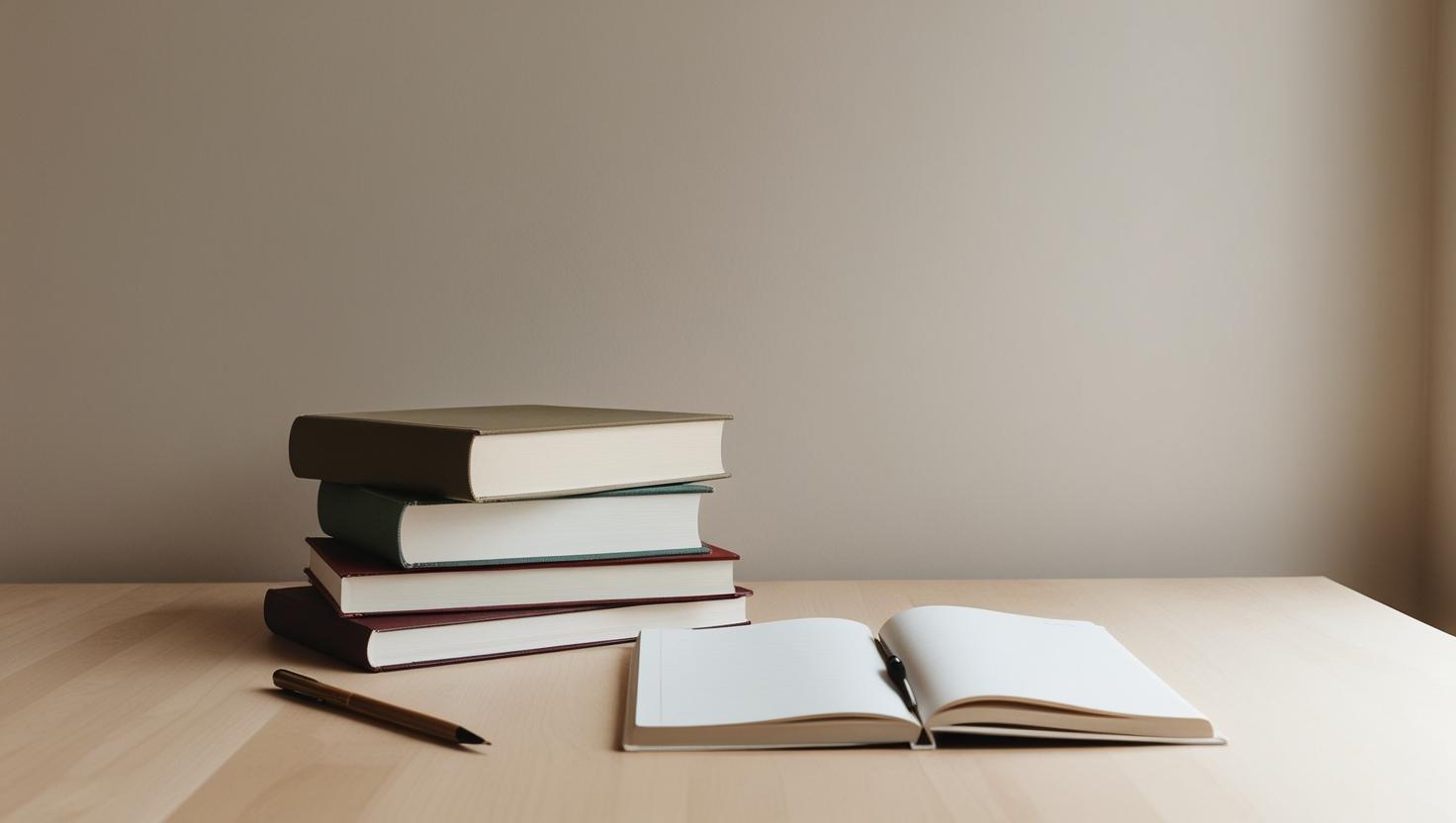資格試験 コンクリート診断士の試験考察

前回記事で長くなり過ぎたため、別途コンクリート診断士試験自体についての考察を書きます。
※自分の主観に基づいた想像を含みますのでご注意ください。

採点についての考察
採点は非公表ですが、施工管理技士試験のように記述にも点数をつけて4択の点数と合算…ではない気がします。
合算の点数で合否を決める場合、全員分の記述を採点し点数を付けなければならず、1点の違いで合否が変わってしまいます。
また、記述の採点は現状AIでなく生身の人間が行っているはずです。
そうすると全員分を複数人チェックで採点、採点基準のすり合わせなど膨大な労力が掛かります。出題内容的に人により判断の分かれる部分も多いですが、施工管理技士試験の二次検定などと比べ試験から合格発表までの期間は大分短いです。
他にも、
- 国家資格と違い申し込み時の返信用封筒にも自ら切手を貼らなければならない
- 国家資格試験と比べて試験会場の案内、人員が少ない
- 数年毎に資格更新費用が発生する
など、受験者数も異なるため単純な比較はできませんが、国家資格試験と比べて予算、人員不足は各所で感じます。
近年の合格率が16%付近で推移していることから、4択の段階で16%に近い範囲で選別を行い、選別した受験者の記述のみを内容全体で見て〇、×の判定ぐらいではないかと予想しています。その〇の割合も皆さんが思っている以上に多いと思います。
記述は4択に時間を掛けすぎてしまった人、少し捻った問いに対応できなかった人、運良く4択の正解数が合格ラインに達してしまい記述の準備をしていなかった人などを削るようなイメージです。
多少のミス、間違いがあっても全体的に筋が通っていれば合格になるとも思われます。実際自分も調査方法で微妙な解答をしても合格しましたし、その他、多少の誤字脱字があっても合格したという人の話も聞いています。
4択の難易度的にも、安定して合格点を取れるぐらいの知識が身に付いていれば十分にコンクリート診断士を名乗れると思いますし、その中で記述が全く書けないという人はほとんどいないと思います。
そもそも施工管理技士、コンクリート主任技士試験などの記述は自らの経験、携わってきた業務を述べますが、コンクリート診断士試験は写真と限られたデータから劣化原因を推定し、その推定から調査方法を立案、その調査方法の結果○○であるとさらに推定し補修方法を立案していく、推定に推定を重ねた解答になります。
出題テーマについて、出題者側では実際に行った調査結果、補修方法も把握していると思いますが、試験で与えられた内容だけで正確な劣化原因、無駄のない最適な調査方法、補修方法など分かるはずがありませんし、出題者側もそんなことは求めていないと思います。
コンクリート診断士の記述問題は、限られた情報の中でどのような推定をして、その推定に対しどのような提案が出来るかという、知識の幅の広さを推し量る試験だと思っています。
そのため、必要なのは正確な答えではなく、ある程度方向性の合った推定、提案ができるかだと自分は考えます。
出題者側についての考察
コンクリート診断士、主任技士は日本コンクリート工学会が主催する民間資格となります。
無機質に感じる試験問題でも、その向こう側には必ず出題者となる生身の人間がいて、出題頻度が高い問題=出題者が身に着けて欲しいと思う知識とも言えます。
コンクリート診断士と主任技士でもそれぞれの試験委員会が実施と運営を担っており、そこにも違いがある気もします。
コンクリート診断士側の人々については受験申込資料内にもある通り、かなり高い意識で資格の地位向上に努めており、有資格者側からするとありがたい話です。
また、直近でも施設の老朽化は重大な社会問題となっており、コンクリート診断士の重要性はより高まると思います。自分が建設業界の資格を上場株式として客観的に見ても、コンクリート診断士は最優先の買い銘柄です。
診断士会という組織も地区ごとにあり、そこでは現状に満足せず貪欲に知識を求め続け、新技術、新材料にも明るい人々が多く、色で言うと赤、オレンジ…といったような熱を感じます。
これから診断士になる人々にも、同様の意識を求めていると感じることもあります。
そのため前回記事の記述分野で自分が書いたソフトコアリング工法、亜硝酸リチウム、それ以外にも有用性を感じる新技術は、参考書、過去問に記載が無くても記述の解答で積極的に活用して良いと思っています。
出題者側はその資格を名乗る人にどういった知識を身に着けて欲しいのか、どういった人であって欲しいのか、そのような目線の考えを持つことも大切だと自分は考えます。
まとめ
コンクリート診断士試験について、自分が思うことは大体言語化したかなと思います。
自分の頭の中だけで何となく完結させていた内容もあり、記事を書くのにかなりの時間が掛かってしまいました。
しばらく時間は空くかもしれませんが、次は合わせて受験する人もいるであろうコンクリート主任技士について掘り下げていく予定です。