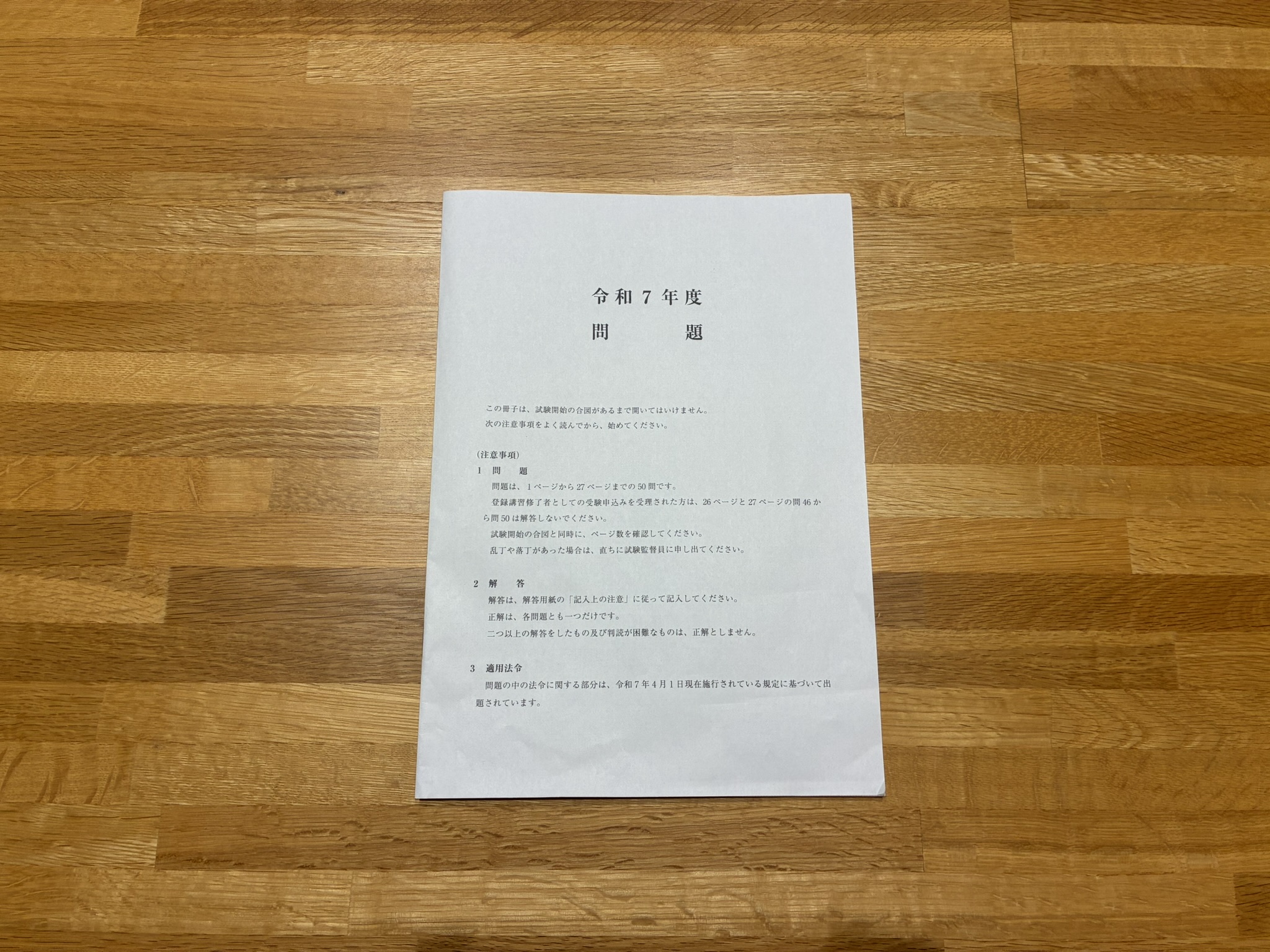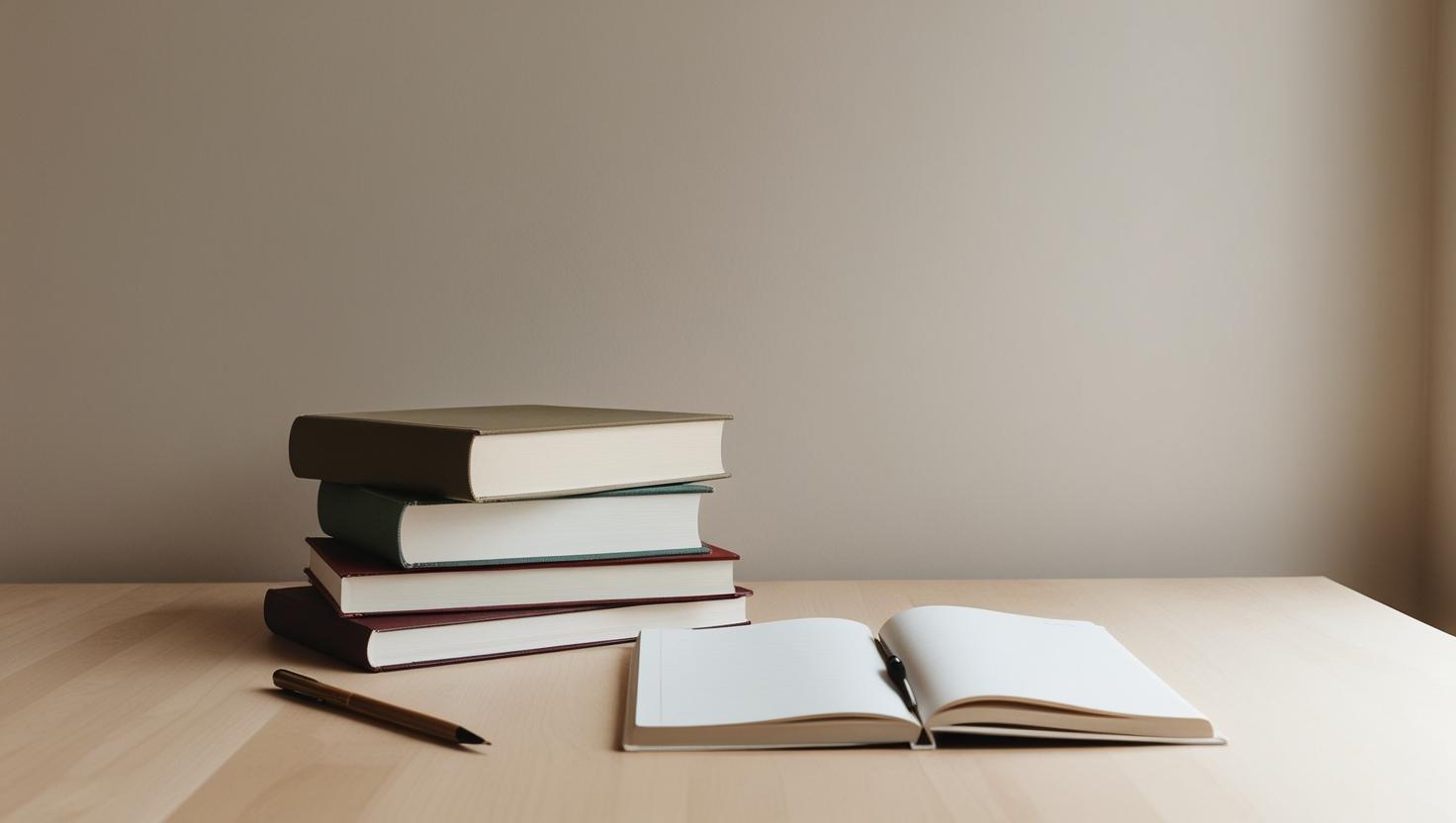資格試験 コンクリート主任技士の試験考察

前回コンクリート主任技士試験の勉強方法、記述文章作成について記事を書きましたが、試験自他の考察についても書いていきます。
※自分の主観に基づいた想像を含みますのでご注意ください。

採点についての考察
基本的にはコンクリート診断士の試験考察で書いた内容と同様です。

考察の要点だけまとめると、
- 記述にも点数をつけて4択の点数と合算ではない
- 4択の段階で近年の主任技士試験の合格率13%に近い範囲で選別を行う
- 記述採点を行うのは4択で選別した受験者のみで、内容全体で見て〇、×を判定する程度
- 記述は多少のミス、間違いがあっても全体的に筋が通っていればOK
といったところです。
記述の解答方法については明確に違いがあり、与えられたテーマに対して、
診断士試験では幅広い知識に基づいた推定、提案をしていきますが、主任技士試験では自分が携わっている業務についての現状把握、課題、それに対して実際に行っている取り組みなどを問われます。
より具体的、実践的な解答というのは建設業の試験全般でのトレンドですが、出題内容的にも主任技士では特にその傾向が強いと思います。
出題者側についての考察
診断士の試験考察でも触れましたが、同じ日本コンクリート工学会が主催する民間資格でも、主任技士試験側からは、診断士側ほどの熱量を感じないというか…ガツガツしていないというか…笑。色で言うと青、グレーといった感じです。
これについては技士、主任技士は1970年頃創設された歴史のある民間資格ということもあり、比較的新しい診断士が特別なだけかもしれませんが…。
主任技士の記述試験のテーマで環境負荷軽減、生産性向上が増えているのも建設業資格全般のトレンド通りといった感じです。
ただ、近年は人手不足問題が取り上げられることも増え、出題内容も生産性向上の割合が若干増えているような気もします。
試験勉強で特定の分野に山を張るのはおすすめしませんが、本当に余裕が無い場合は記述の勉強時間を高耐久2、環境3、生産性向上5、ぐらいに割り振るのも一つの手かもしれません。
試験合格者の考察
自分が以前所属していた会社では主任技士の不合格者が多数おり、合格率13%前後の試験であることを考慮しても多すぎるぐらいでした。
そこで主任技士の合格者の内訳について、自分の独断と偏見を元に考察したいと思います。
まず主任技士受験者についてですが、大きく下記2つに分かれると思っています。
- 工場、メーカー、試験所などに勤務しており、技士の延長で受験する人
- ゼネコン、コンサルなどで自身の知識探求や箔付けのために受験する人
①の人については、社内で受験を推奨されていて、個人の意思関係なく受験申込をしている場合も多く、さらにこれまで経験した資格試験は技士のみという人も多いと思います。
②に人については、一級施工管理技士、一級建築士、技術士など、主任技士より遥かに必要な国家資格があり、主任技士にまで手を伸ばす人々は当然それらを取得済みで、しかも複数取得済みの場合も多いと思います。(当然技士も)
資格試験の勉強については、知能×効率×時間の掛け算だというのが自分の結論で、この中の効率という部分については受験勉強とは違ったノウハウ、慣れも必要となり、①の保有資格が技士のみの人、②の技士の他、複数の難関国家資格を保有している人とでは、この部分で非常に大きな差が生まれてしまいます。
仮に知能を同等として、効率面で大きな差があった場合、①の人が②の人に勝つにはその差を埋める分の勉強時間が必要となります。
②の人は有名大学出身で地頭も良いなんてことも割とある話で、もし知能ですら②の人に劣っていたとしたら…恐ろしいですよね。
必ずしも②の人に勝たなければ合格できないというわけではありませんが、何度も言っているように主任技士は上位13%前後を合格とする相対評価の試験で、他受験者と13%の合格枠を奪いあう競争とも言えます。
人としての優劣をつけるわけではありませんが、受験者全体での割合は少ないにしても②の人々の多くが合格枠内に入り、残りの枠を①の人々で分け合うような構図になってしまっている現実は理解する必要があると思っています。
自分が以前所属していた会社の不合格者も①に分類され、多くはそもそも資格試験勉強に限らず、社会人になってから勤務時間以外で何かを自主的に学ぶ、ということができない人が多かった気がします。
そもそも②の人々はこれまで何百時間、人によっては何千時間と資格試験勉強をしてきて、それでも満たされずコンクリート関連の資格に手を伸ばすような怪物達です。当然誰に言われるでもなく勉強しますし、時間ですら負けていたら勝負になりませんよね…。
①の中にも当然知能の高い人はいますが、基本的に大人になって知能が変化することは無く、合格するためには自身の経験外の情報により効率を上げる、効率で劣る場合はその分勉強時間を増やす、といった工夫が必要になると思います。
手前味噌ですが、少しでもその効率を上げる、時間を増やすきっかけになればと思い、当ブログでは資格試験関係の記事を書いています笑。内容の合う合わないはありますし、最終的には本人次第ではありますが…。
色々言いましたが、それを乗り越えて①の人が手にした合格というのは、そこまでの過程を含めて本当に価値があり、生涯誇れる経験だと思います。
ちなみに自分は①、②以外で、大した知能はなく技術士などの超難関資格を持っているわけでもありませんが、主任技士合格に繋がるノウハウはそれなりに持っており、試験本番まで勉強の優先度を上げるくらいの理性はあったと自負しています笑。
まとめ
コンクリート主任技士についても思っていたことは一通り言語化できたかなと思います。
一級土木、建築施工管理技士試験についても書こうと思っていましたが、近年の試験問題に目を通してみたところ、出題形式、内容が若干変わっており、基本は一緒のため対応自体はできますが、再分析するのにかなり手間が掛かりそうですね。
特に建築の記述について、ニュースになった大手ゼネコンの改ざんトラブルなどの影響だと思いますが、品質管理もトレンドになりそうなのが非常に興味深いです。
ですが、単なる趣味でやるには苦行過ぎるため、しばらくは他のことに注力します!笑
いつの日か気が向いたときには…。