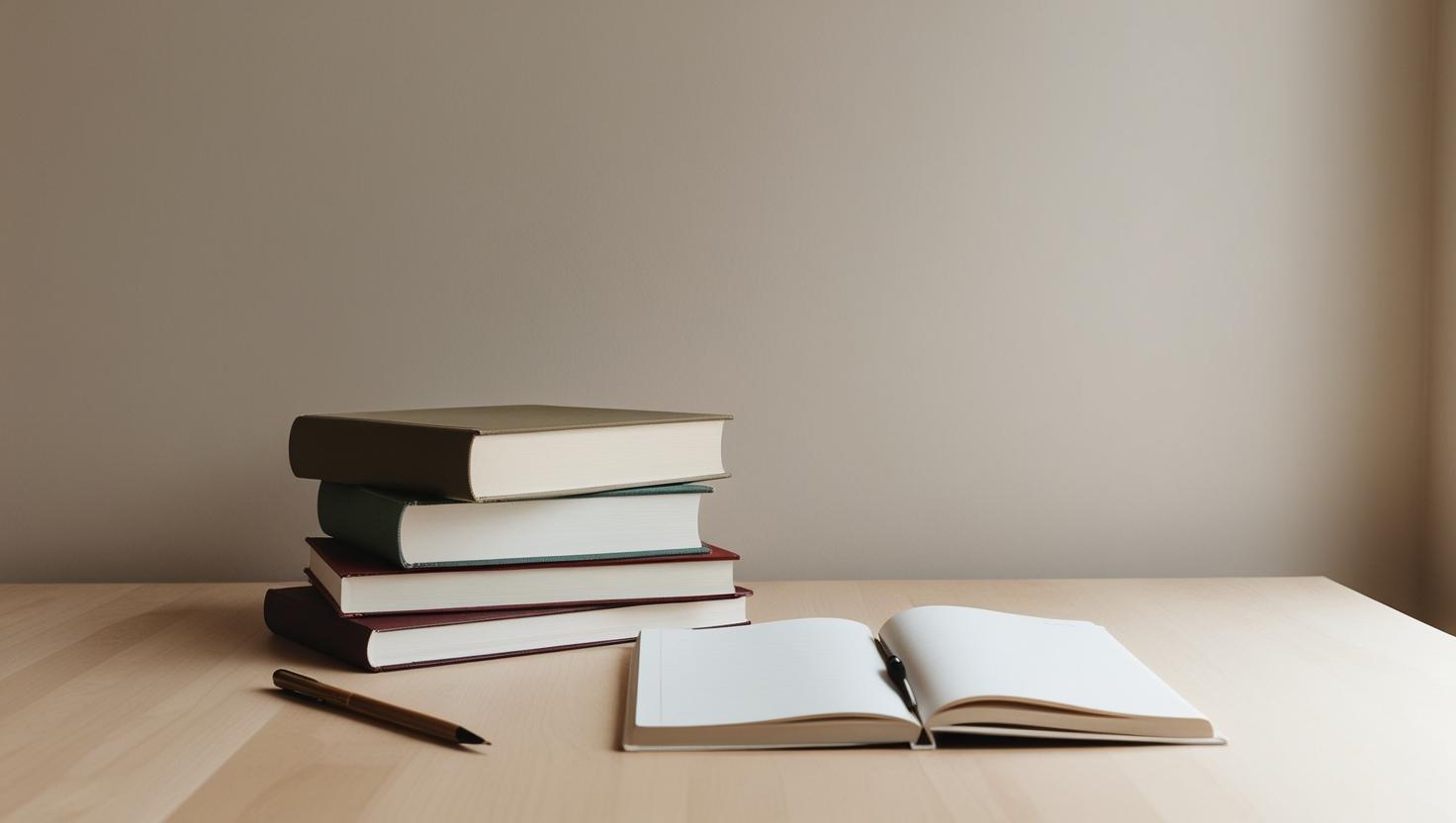令和7年度宅地建物取引士試験を終えて
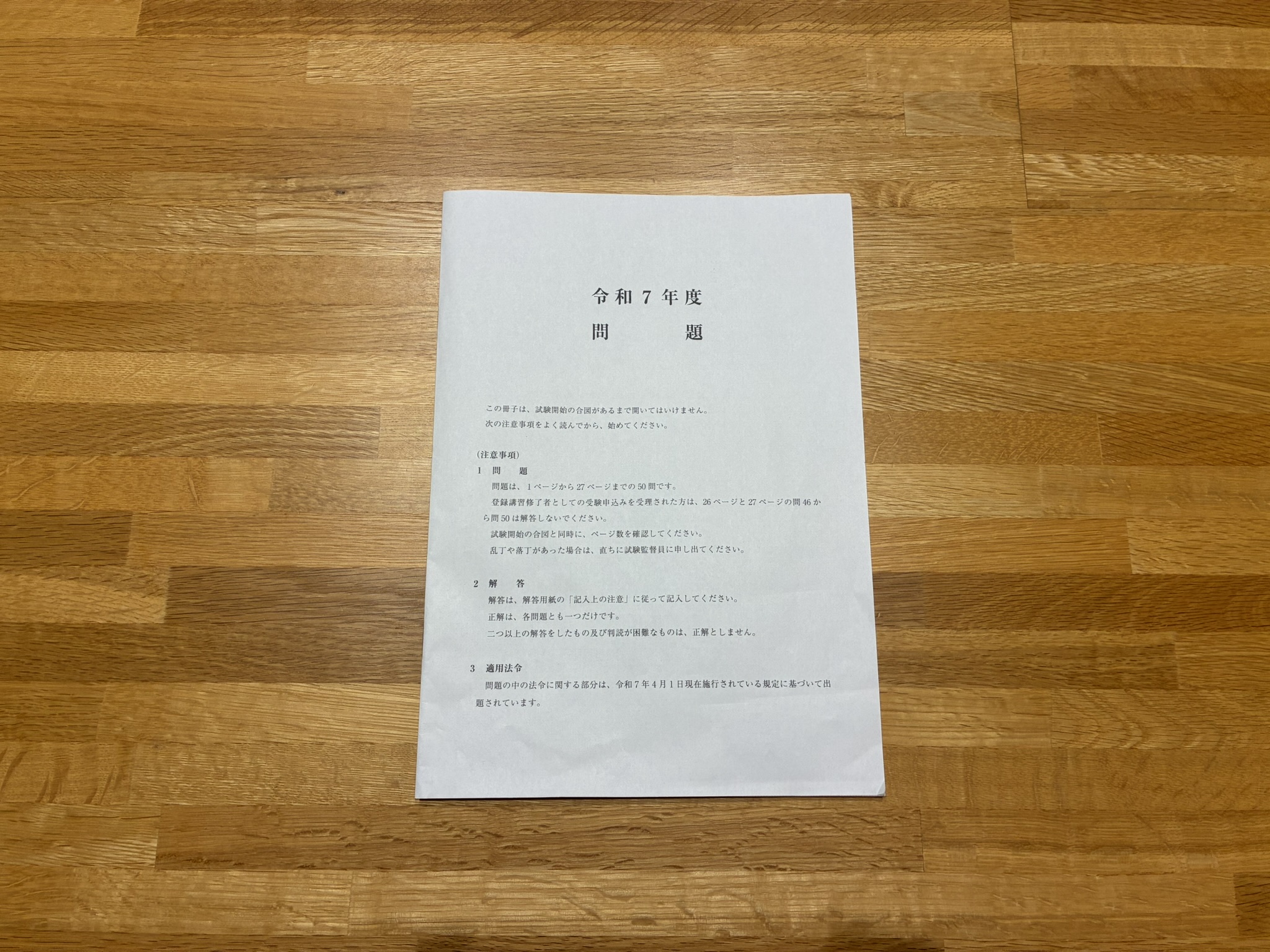
昨日行われた宅建士試験を受験してきました。
試験までの流れ、試験を終えての自己採点結果、試験内容の所感を書いていきます。忘れないうちに…。
試験まで
昨年
実は昨年コンクリート主任技士とダブル受験しようと参考書を購入し、宅建業法と法令上の制限の半分ぐらいまでは、初期段階の0→1にする勉強をしていました。
…が、夏頃から忙しくなりサービス残業、休日稼働(無給)も大幅増加し、さすがにダブル受験は厳しく、間接的に業務に関係するコンクリート主任技士のみ受験しました。
今年
今年は会社を辞めて時間ができ、既に手は付けているし、どうせなら宅建を取ってしまおうと夏頃から勉強を再開しました。
とは言っても誰の目があるわけでもなく、登山などの趣味を最優先にして勉強にはあまり時間を割り振らず、9月下旬頃にはそもそも当日試験会場に行くか迷っているレベルでした笑。
そこから合格するには勉強に専念せねばならず、それは貴重な紅葉時期の登山との引き換えを意味します。
そうして悩んでいたところ、宅建試験までの山の天気予報が全体的に悪く、勉強を最優先にすることに決定。
有り余る時間を活用して頑張りました!
試験を終えての自己採点結果
自己採点結果 41/50
※Xで見たTACの解答速報を参照しており、多少前後する可能性あり
分野別だと、
- 宅建業法 16/20
- 権利関係 14/14
- 法令上の制限 5/8
- 各種税 1/3
- 免除科目 5/5
45点以上を目標にしていましたが、稼ぎどころの宅建業法で想定を下回る8割…法令上の制限、各種税も問20~24の5問連続不正解でごっそりやられました。
しかし、権利関係がまさかの満点!これも想定はしておらず。
各所の合格点予想は34点前後で、目標の45点には届きませんでしたが合格はできそうです。
というか建設系資格に比べて情報が早すぎる笑。流石は人気資格…!
以下、分野毎に所感を書いていきます。
宅建業法
自己採点 16/20
統計問題の後はここから解き始めましたが、個数選択問題が多すぎてビビる…!
とはいえそれなりには解けたつもりで、試験終了後は19点ぐらいの感覚でしたが、自己採点結果は16点…。
間違えた4問は全て個数選択問題で、正解した問題も含め改めて確認すると、
- 長期の空き家等の媒介特例
- 罰則と監督処分の対象
- 重要事項説明
- 宅建業法以外の法律
などで、自分があまり深堀りしていない部分が出題されました。
問30の選択肢1は、35条書面には売主側の全ての宅建業者(宅建士)の記名が必要だと思っていましたが、自分の参考書を見返すと確かに37条書面には全ての~記載があるものの、35条書面には記名としか記載無し。
正確な解説までは見つけられませんでしたが、35条は1社の記名で良かったということなのでしょうか…?ここは各所で意見が割れており、今後の情報を待ちたいと思います。
問42の選択肢1、二つ以上の都道府県で合格した者については、
- 試験日の遅い都道府県しか登録を受けられない=それを確認するには試験日も含めた合格者一人一人の情報を、全都道府県一括で複数年分保管していなればならない
- 膨大な数の受験者がいる=合格者も膨大で、中には合格後に登録しない者もいる
- 合格→登録→宅建士証交付まで各都道府県毎の管理
といった想定から、せいぜい登録の際に他県の登録者情報と照合し、重複が無いか確認する程度ではないかと×にしました。実際のところは分かりませんが。
稼ぎどころの宅建業法で16点というのは想定を大きく下回りましたが、改めて精査してみると、自分の勉強方法では勉強量を増やしてもこれ以上の点数を取るのは難しかったと思います。
実際過去と比較しても難しい気がしますし、これで19、20点取れる人はどのぐらいいるのだろう…受験者の点数分布も気になります。
権利関係
自己採点 14/14
権利関係は個数問題が無いイメージでしたが、問3でまさかの…しかも取消しと無効を混ぜたいやらしさ。
ですが、これについては取消しできる条件、取消しの前と後での違いなどを、感覚ではなく理屈で整理して覚えていれば問題無く解けたと思います。
満点だったのは正直運もあり、分からない選択肢もあったが正解の選択肢は知っていた、というのが数問ありました。
権利関係はざっくり見返した中でも、
- 問1 解除前の第三者は登記ありで保護、解除後の第三者とは対抗関係(どちらも登記の早いもの勝ち)
- 問4 被害者側のみ損害賠償請求債権を自働債権として相殺可能
- 問8 共有者の一人が持分を放棄しても、国庫に帰属せず他の共有者に帰属
- 問12 造作買取請求権を行使できない特約は有効
- 問14 所有者からの分筆登記申請が無い場合、登記官は職権で分筆登記しなければならない
など、過去問で学んだ知識(フレーズ)があれば、選択肢を全て読む前に一撃セットプレイで即答できる問題が多かった気がします。
加えて問9はあこ課長の語呂合わせで問題ごと一撃セットプレイ!これホントに優秀…。
権利関係で想定より点数を取れた人は、自分の他にもそれなりにいるのではないでしょうか。
法令上の制限
自己採点 5/8
暗記の多い都市計画法、建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法は正解できて良かったですが、その他は知識不足…。
問22の国土利用計画法の事後届については、抵当権設定、贈与は該当しないというのが中々覚えられず、当日朝に権利性、対価性、契約性のないものは該当しないと復習していました。
賃借権→該当する!で反射的に食いついてしまいましたが、その前の対価の授受を伴わず、を見逃しており不正解…これは落としてはいけない問題でした。
元々そこまで自信のある分野では無く、ギリギリ及第点といったところです。
各種税
自己採点 1/3
限られた時間の中では比較的点数に繋がりやすいと思い、税分野は当日朝にも再確認していましたが、正解できたのは1問のみ…。
問23の登録免許税は参考書など見返してもよく分からず。
問24は選択肢1、4が明らかな×、選択肢2はよく分からずという中、固定資産税定番の30万-20万-150万があり、心の中でガッツポーズしながら選択!
自己採点で×になり、速報のミスかと思って問題を確認すると、課税標準→固定資産税額に笑。完全な引っ掛け問題で見事に釣られました…。
税は満点を取るつもりだったため、想定を大きく下回りました。
免除科目
自己採点 5/5
問48の統計問題は、直前暗記で試験開始後忘れる前に即解答。その他も過去問を解いていれば問題無く正解できるものばかりでした。
この免除科目を間違うと免除者と差がついてしまい、上位○○%が合格になる相対評価の試験ではマイナスからのスタートとなってしまいます。
絶対に落とすわけにいかず、無事5点取れて良かったです。
まとめ
知識が不十分なところもあったとは言え、高得点を目指すと一気に難易度が上がる試験だなと改めて感じました。これは宅建士試験に限らずですが…。
また、記述の無い資格試験も久々でしたが、マークシートのみだと4択問題の正解選択肢を狙い撃ちした一撃セットプレイが強力ですね。
特に今回は、権利関係でセットプレイを決められたかどうかで試験時間の配分、合計点数に大きな差がついたと思います。
宅建士試験は建設系資格と比べて圧倒的に受験者が多く、参考書、動画、サイトなど高品質な教材が次々生まれ、SNSの普及もあり、近年の合格点推移からも従来の出題内容は受験者達に攻略されつつあるのかな、と感じます。
しかしながら、出題内容を大きく変えニッチな問題を増やし過ぎると、今度は出題者側が願う宅建士を名乗る上で身に付けて欲しい知識、というのがブレてしまいます。
結果、理解の深さを測るために個数選択問題を増やしていく、というのはある意味自然な流れなのかもしれません。
想像を含めて色々書きましたが、現時点での宅建士試験に合格する、という一点においてはある程度攻略完了し、自分の中で効率が良いと思える勉強方法、使用教材も確立できたと思います。
結果発表後を目安にブログ記事としてまとめる予定です!